2020年6月、兵庫県宝塚市の静かな住宅街で、信じ難い惨劇が起きました。ある男がボーガン(クロスボウ)を手に自分の家族を次々と襲い、祖母・母・弟の3人の命を奪い、さらに伯母にも重傷を負わせたのです。親族同士で起きたこの事件は日本中に衝撃を与え、加害者である野津英滉被告(犯行当時28歳)の心の闇と、事件をめぐる裁判の行方に大きな注目が集まりました。事件後、クロスボウが規制される法改正が行われるなど、社会にも波紋を広げたこの悲劇。その裁判で何が明らかになり、どんな判決が下されたのか――そして私たちはこの事件から何を考えるべきなのでしょうか。
事件概要:ボーガンで3人を殺害、1人重傷の衝撃
宝塚市の民家で起きたクロスボウ襲撃事件の現場。2020年6月4日、野津英滉被告(当時28歳)は自宅で突然ボーガンを発射し、同居していた祖母(75歳)・母(47歳)・弟(22歳)を次々と射ち殺しました。さらに野津被告は現場から車で約1km離れた伯母(55歳)の家にも向かい、伯母にもボーガンの矢を放って重傷(首の骨折など)を負わせました。矢が刺さったまま逃げ出した伯母を近所の人が発見し通報、駆け付けた警察によって野津被告はその場で逮捕されました。
使用されたボーガンという武器の異様さも相まって、事件現場は騒然となり、多くの人々が「なぜ家族に向けて矢を放ったのか」と言葉を失いました。犯行に使われたクロスボウは高い殺傷能力を持ち、当時は誰でも購入・所持できたため、この事件を機に警察庁は規制の検討を開始。2022年には銃刀法が改正され、クロスボウの所持に許可が必要となる制度が施行されています。しかし、道具の規制以上に社会を揺るがせたのは、「家族」という最も身近な存在を襲った深い悲しみと衝撃でした。

裁判の展開:明かされた動機と被告の告白
その後の裁判員裁判で明らかになったのは、野津被告自身が語った驚くべき犯行動機でした。野津被告は逮捕後、犯行について淡々と事実を認め、その理由を「死刑になりたかった」からだと供述しました。すなわち、自ら死刑判決を受けて命を絶たれるために、自分の家族を手にかけたというのです。この供述に基づけば、彼は当初から死刑を望み、確実に極刑となるよう計画的に犯行に及んだことになります。実際、大学で「3人殺害でも死刑にならない場合がある」と聞いた野津被告は、死刑を確実にするため第四の犠牲者として伯母も標的に加え、「4人殺せば死刑になると思った」と語っています。
裁判ではこの異様な動機が詳しく掘り下げられました。野津被告は事件前、大学を休学して引きこもりがちになり、将来を悲観して自殺も考えたといいます。しかし、「自分だけが死ねば家族は事件の原因に向き合わず好き勝手に言うだろう」と想像すると苦しくなり、「ならば全員殺してしまおう」と発想を歪ませたとされています。自分の苦しみを世間に知ってもらいたい──そんな歪んだ願望が、家族4人を標的にした惨劇へと彼を駆り立てました。
公判中、野津被告は終始うつむきがちで、多くを語ることはありませんでした。しかし証言などから浮かび上がったのは、家族への複雑な感情です。野津被告は「自分の家族は殺されて当然」「後悔していない」「早く死刑になりたい」といった趣旨の発言もしており、その冷淡さに傍聴席は息を呑みました。生き残った伯母が裁判で被告と向き合った際も、野津被告は頭を抱えるように下を向き、謝罪の言葉は最後まで聞かれなかったと言います。
検察と弁護側の主張:極刑か、それとも情状か
この裁判の争点は、野津被告にどの程度の刑事責任能力が認められるか、そして量刑を死刑とすべきか否かでした。事件の凄惨さから、検察側は冒頭より「計画的かつ冷酷な犯行だ」として極刑を主張。実際に神戸地裁での論告求刑公判で、検察側は死刑を求刑しました。検察は野津被告について精神鑑定の結果「事件当時、完全な責任能力があった」と指摘し、発達障害の影響で動機が変わることはなく計画的犯行は十分可能だったと強調しました。また「被告の自閉スペクトラム症(ASD)は動機にほとんど影響していない」とし、犯行前に一時躊躇したものの自身を制御する能力は十分あったと主張。何より犯行の動機自体が「死刑になりたい」という自己中心的なものだとして、「命をあまりにも軽んじている」と強い非難を浴びせました。
一方、弁護側は野津被告の生い立ちや精神状態に焦点を当て、事件当時の彼は心神耗弱(著しく判断能力が低い状態)にあったと主張しました。野津被告には自閉スペクトラム症や強迫性障害といった発達障害があり、それらの特性が動機の形成に強く影響していたため、責任能力は限定的だったという立場です。弁護側は「極刑ではなく更生の道を残すべきだ」と訴え、具体的な量刑として懲役25年が妥当であると提案しました。これは、日本の刑法で有期刑の上限が原則20年(併合罪では30年)である中、極めて重い有期刑を科すことで死刑を回避しようとする主張でした。
検察と弁護人の主張は真っ向から対立し、「家族3人を殺害し1人を負傷させた犯行に死刑は避けられない」という厳罰論と、「発達障害ゆえの歪んだ心理状態を考慮し情状を汲むべきだ」という寛典論が法廷で戦わされました。裁判員を含む裁判所は、この難しい判断に直面することになります。
神戸地裁の判決:無期懲役に込められた理由
2025年10月31日、神戸地方裁判所で判決公判が開かれました。注目の量刑について、裁判長・松田道別(まつだ・みちわけ)は慎重に言葉を選びながら主文を告げました。「被告人を無期懲役に処する」――求刑された死刑ではなく、無期懲役の判決です。法廷に緊張が走る中、松田裁判長は判決理由を詳細に述べました。その内容は、事件の凶悪性を厳しく指摘しつつ、一方で被告の精神面にも一定の理解を示すものでした。
まず松田裁判長は、野津被告の責任能力について「犯行時、被告は自身の行動を十分に制御し得ており、心神耗弱は認められない。完全責任能力があった」と明言しました。被告が殺害を実行する際、一瞬ためらった様子もうかがえることからも、犯行を理性で抑制する力は保持していたと判断されたのです。さらに「動機は家族関係の現実的な問題に根差したもので、理解不能なものではない」と指摘され、動機自体は妄想の産物ではなく家庭内の葛藤という現実に沿ったものである点も強調されました。
そのうえで判決は、量刑判断において以下のような相反する事情を考慮したと述べています。一つには、犯行が極めて計画的で悪質だという点です。殺傷能力の高いクロスボウを凶器に選び、殺害の順序まで検討して実行した計画性、さらに死刑になるために血縁の伯母にまで矛先を向け重傷を負わせた結果は、同種の事件の中でも「重い部類」に入ると厳しく非難されました。野津被告の動機についても「伯母も巻き込んで死刑になろうとした自己中心的なものだ」と断罪し、その罪深さを強調しています。
しかし他方で、裁判所は野津被告の置かれた特殊な心理状態にも目を向けました。判決文では「母や家族によって心理的安定が脅かされた結果、生来のASD(自閉スペクトラム症)や強迫性障害の重い症状が現れた」として、精神障害の影響を重要視する旨が述べられました。つまり、犯行動機が形成される過程で発達障害ゆえの極端な思考傾向が影を落としていたことを認めたのです。また野津被告の犯行には無理心中的な要素(自分もいずれ死刑で命を絶たれる前提で家族を道連れにする心理)があること、そして犯行が家庭内にとどまり社会に広く危害を及ぼすものではないことも指摘され、「死刑という刑を選択することが真にやむを得ないとまではいえない」と結論づけました。判決理由の中には、「自殺ではなく『死刑になる』という極端な思考に至ったのはASDの症状によるもので、自力では抗い難い状況だったことは被告を一方的に非難できない」という趣旨の言及もあり、発達障害の特性が異常な動機形成に繋がった点で被告にも抗しがたい事情があったことが汲み取られています。
このように神戸地裁は、犯行の計画性・重大性と被告の精神的特性という両面を天秤にかけ、最終的に無期懲役という結論を導きました。3人もの命が奪われた事件で死刑が回避された背景には、「家庭内の事件」であることや「精神障害の影響」が斟酌されたことがうかがえます。判決後、裁判長は「社会的影響は大きいが、死刑適用は慎重であるべき事案だった」と述べたと報じられており、その声は司法が示したひとつの判断基準として受け止められました。
判決確定と揺れる心情:控訴断念という決定
死刑を求めていた検察側の反応も注目されました。判決直後、神戸地検の副検事は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応する」とコメントし、控訴(判決に不服として上級裁に審理を求めること)も含め対応を検討する姿勢を見せました。しかし最終的に検察は控訴を断念します。判決から2週間後の11月中旬、検察側は期限までに控訴せず、無期懲役判決が確定しました。神戸地方検察庁はその理由について「判決内容を仔細に検討し、証拠を総合的に判断した結果、控訴理由が見出せなかった」と説明しています。極刑を求めた検察が上級審での争いを諦めたことは、この判決の重みを物語るものでもあります。
一方、弁護側もまた控訴しませんでした。被告人野津英滉は一審の無期懲役を受け入れる形となり、これにより裁判は終結しました。死刑か無期懲役かで揺れた裁判員裁判は、司法関係者の間でも議論を呼びましたが、最終的に下った判断は「被告を社会から隔離し、一生をかけて罪と向き合わせる」というものでした。
判決確定を受け、野津被告はこの先生涯にわたり刑務所の中で過ごすことになります。彼が奪った命の重さと向き合い続ける長い年月が始まったのです。その現実は、本人が「望んだ」死刑とは異なる形で科せられた贖罪の日々といえるでしょう。
生き残った伯母の言葉:偏見なき社会への願い
この事件で唯一の生存者となった伯母は、裁判を通じて計り知れない苦しみと向き合ってきました。判決後、伯母はメディアを通じてコメントを発表しています。そこには、無念にも命を奪われた家族への想い、そして甥である野津被告に対する複雑な感情が滲んでいました。
伯母はまず、「3人は殺されてしまったがために自分たちの言い分を述べることができず、裁判の資料はほとんど彼(被告)の説明によるものだった。その結果、彼が家族に苦しめられていたということが過剰にフォーカスされてしまっていた」と指摘しました。亡くなった母・祖母・弟たちには反論の機会がなく、法廷では加害者の語る家庭の問題ばかりが強調されてしまったことへの無念さがうかがえます。さらに伯母は、奪われた命の重みと向き合いながらも、こう続けました。「彼も大切な家族です。罪と向き合わせることで償わせるという裁判所のご判断は、私にも響きました」。自身をも傷つけた加害者であり甥でもある野津被告について、憎しみだけでなく「大切な家族」と表現した伯母の言葉からは、計り知れない葛藤と、それでも失われない血縁の情が伝わってきます。
そして伯母は、この事件を社会が受け止めるにあたり最も伝えたかったであろうメッセージを述べました。それは、障害を抱える人々への偏見や誤解を生まないでほしいという切実な訴えでした。伯母は言います。「決して、障害や特性を持つ方が危険であるということではありません。どうか、障害や特性について誤解がなされないように願いたいです」。裁判では被告人の発達障害や精神障害が繰り返し議論されましたが、それらはあくまで背景要因であり、障害があるから人を殺めるのではない──伯母はそのことを誰よりも理解していたのでしょう。自身も深い傷を負いながら、「障害がある人=危ない人」という偏見が社会に広まることのないよう、心を振り絞るように訴えたのです。
この伯母の言葉は、裁判を取材した記者や多くの市民の胸にも深く刻まれました。「私も報道に携わる者として、そういった誤解がなされないよう一層の注意を払いたい」と記者が述べているように、事件を伝える側にも大きな責任があります。伯母のメッセージは、被害者家族の痛切な願いであると同時に、社会全体への問いかけでもあります。私たちはこの事件を他人事とせず、障害や心の病を抱える人々に対する理解と支援について改めて考えなければならないのではないでしょうか。
被告の背景と心理:浮かび上がった発達障害と家庭環境
裁判を通じて明らかになった野津英滉被告の生い立ちと心理的背景は、この事件の根底にある闇を浮き彫りにしました。その人生を振り返ると、幼少期から家族関係や自身の特性に多くの困難を抱えていたことがわかります。
野津被告の両親は弟が生まれてすぐに離婚し、以後は祖母・母・弟との4人ときどき父方祖父母…という複雑な家庭環境で育ちました。母親は先天的な発達障害(アスペルガー症候群)を抱えており、弟は多動性障害(ADHD)があったといいます。そして野津被告本人も小学生の頃に自閉症スペクトラム(ASD)と診断されていました。幼い野津少年にとって、家庭は決して安定した場ではなかったようです。母親は弟にかかりきりで、兄である被告は疎外感を抱くこともあったでしょう。実際、母と弟は人目もはばからず舌を舐め合うようなスキンシップを日常的に交わしており、食事もカップ麺に白飯を乗せただけの奇妙なものが出されるなど、家庭生活は世間一般とはかけ離れていました。野津被告はそれが当たり前だと思っていましたが、小学校で他の子のお弁当と比べ「うちは少しおかしい」と気づくようになったといいます。弟に対しても「わざと自分の嫌がることをする生意気なガキだ」と憎々しげに語り、母に対しては中学生になる頃から「母親としての資格がないのでは」と疑うようになり、ストレスが溜まって暴力を振るうようになってしまいました。家庭内暴力から逃れるように母が家を出た時期もあり、野津被告の心はますます孤独と憎悪を深めていきました。
大学に進学してからも彼の抱える闇は晴れず、次第に心身の不調が顕著になります。再び母親が家に戻ってきた頃から、野津被告は「頭の回転が遅くなり、脳が思うように使えない」「腸の感覚がおかしく、排泄が自分でコントロールできない」といった症状に悩まされました。病院で検査しても異常はなく、原因が分からないまま考え込むほどにストレスは増大。日常生活もままならず将来を悲観して、自室に閉じこもりがちになりました。このように、野津被告の人生には発達障害による生きづらさと、それを支えきれない家族関係の軋轢が常につきまとっていたのです。
裁判では、3人の精神科医・心理士による詳細な鑑定結果が示されました。その中で野津被告の心理プロフィールとして浮かび上がったのは、平均以上の知能を持ちながらも対人理解が極端に苦手で、強いこだわりと繊細さを併せ持つ人物像でした。知能検査では11歳時のIQが106、18歳時には120と平均(100)を上回っており、大学入学やアルバイト経験もあったことから社会適応は一見可能だったことが示されています。しかし「心の理論」と呼ばれる他人の感情や意図を読み取る試験では9割を誤答し、対人的な柔軟性の低さが露呈しました。また「バウムテスト」という一本の木の絵を描く心理テストでは、1時間以上も細部まで描き込む強い粘着性(こだわり)を見せ、文章完成法テスト(SCT)では与えられた未完成文に対し「子どものころは——『一人だった』」「嫌いなのは——『母』」といった回答をしており、被告の心が常に家族、とりわけ母への嫌悪感に支配されていたことが浮き彫りになりました。
鑑定医らは最終的に、「被告人には自閉スペクトラム症と強迫性障害の症状が認められる」と診断しました。その上で3名の専門家は口を揃えて強調したのは、「これらの障害が犯行動機の形成過程に影響を及ぼしているものの、最終的な動機は積み重なった家族への感情が原因で、違法性の認識などに問題はない」という点でした。言い換えれば、発達障害ゆえの極端な思考傾向が犯行の背景にはあるものの、だからといって善悪の判断ができなかったわけではなく、最終的には彼自身の家族に対する恨みが犯罪を決意させたというのです。この点は裁判所の判決判断とも合致していました。
「自閉症だから事件を起こすのではない」――鑑定に関わった医師の一人が述べたこの言葉は非常に印象的でした。衝撃的な事件の内容や特異な家庭環境に目を奪われがちですが、決して発達障害そのものが暴力を生む原因ではないのです。社会の中で実際に起きた一つの事件として偏見なく向き合い、正しい理解を持つことが求められていると専門家たちは訴えました。裁判員として参加した市民もその点に真摯に向き合い、被告の特性について積極的に質問を投げかける場面が見られました。専門家の説明に耳を傾け、障害特性と犯行の関係を理解しようと努める姿は、裁判員制度の意義を感じさせるものでもありました。
野津被告の生い立ちと心理をひも解くとき、私たちはこの事件を単なる猟奇的な家族殺しとして片付けることはできません。そこには、支えを必要としていた一人の青年が孤立し、家族との関係が歪んでいく中で追い詰められていった現実があります。しかし、どんな事情があろうとも3人の肉親の命を奪った罪は決して許されるものではありません。裁判を通じ、野津被告も自身の深層心理では罪の重大さに気づいている可能性が示唆されました。入院治療中に意識が朦朧とした際、彼が弟に「悪かった(ごめん)」と謝罪するような言葉を漏らしたとのエピソードも紹介され、心の奥底では後悔の念が全くないわけではない、と専門家は分析しています。その「本心に蓋をしている」という彼の姿は、極刑を望むと強がる表の顔と、自責の念に苛まれる内なる声との葛藤を感じさせます。
社会への示唆:深い悲しみを未来につなげて
3人もの家族の命が奪われた宝塚ボーガン殺傷事件。その裁判の結末は、極刑ではなく無期懲役という形で決着しました。この判決は、司法が犯罪と精神障害の問題に対して一つのバランスを示した例と言えるでしょう。判決理由にある「死刑選択が真にやむを得ないとはいえない」という言葉の背景には、犯罪の重大性とともに、加害者が抱えていた精神的苦悩や家庭環境への理解が垣間見えます。無論、どんな事情があっても犯行が許されないのは当然ですが、だからこそ死刑適用には慎重な判断が下されたのです。
事件を振り返るとき、私たちは何よりもまず犠牲となった3人の尊い命と、遺された家族の深い悲しみに思いを致さねばなりません。同時に、この事件が社会にもたらした課題にも目を向ける必要があります。それは、精神疾患や発達障害を抱える人への理解と支援、そして家族という閉じた環境で起こる問題をどう早期に察知し防ぐか、という問いかけです。伯母の訴えたように、障害がある人への偏見や誤解を避けることは大前提です。そのうえで、周囲の人々や支援者が適切に関わり、孤立を防ぎ心のケアを行う体制づくりが求められています。事件後、地域の福祉関係者からは「もっと早く家庭の異変に気づけなかったのか」という声も聞かれました。行政や支援機関、そして私たち一人ひとりが、周囲の「生きづらさ」に目を配ることの大切さを痛感させられます。
裁判で示された事実と判決は、私たちに様々な感情を抱かせます。怒り、悲しみ、そしてやるせなさ──しかし、どんな感情も亡くなった方々を取り戻すことはできません。ただ、この悲劇を無駄にしないためにできることがあるとすれば、それは学ぶことではないでしょうか。事件から、家庭内の問題に社会がもっと目を向ける必要性を学ぶ。発達障害を持つ人への理解と適切な支援のあり方を学ぶ。そして、犯罪と向き合う司法の在り方についても考える。野津被告のように心に闇を抱えた人を一人にしないために、私たちができることは何か──重い問いが突きつけられています。
最後にもう一度、伯母の言葉を胸に刻みたいと思います。「障害や特性を持つ方が危険なのではありません。どうか誤解のないように」。この訴えを社会全体で真摯に受け止め、誰もが安心して生きられる共生社会を目指すことこそ、亡くなった方々へのせめてもの供養であり、また加害者が二度と生まれない未来への一歩となるのではないでしょうか。事件の悲劇と裁判の記録は、私たちに家族のあり方、心の健康、そして司法の役割について深い問いを投げかけ続けています。


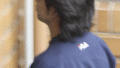

コメント