1981年6月下旬、宮崎県日向市の海岸で、やせ細った初老の男性が保護されました。彼は三日三晩も飲まず食わずで松林に潜み、台風で荒れる海岸を彷徨っていたのです。警察官が声をかけると、男性は力なく倒れ込みました。その男こそ、北朝鮮から密かに送り込まれたスパイ、斉藤幸雄(黄成国)でした。当時62歳の彼は、祖国へ戻るため工作船を待っていましたが、台風による荒天で迎えが来ず、極限状態に陥っていたのです。こうして発覚したのが「日向事件」と呼ばれる北朝鮮スパイ事件でした。警察に保護された黄は、取調べで思いもよらない「完全自供」に至ります。そこには、人間同士の心の通い合いがありました。ある朝鮮語のできる取調官が、弱り切った黄を風呂に入れて背中を流し、朝鮮半島の古くからの風習である義兄弟の契りを交わしたのです。警察官の真摯な姿勢に胸を打たれた黄は、ついにすべてを語り始めました。北朝鮮の工作員が日本で行っていた秘密活動、その驚くべき実態が明らかになったのです。
事件の経緯(いつ、どこで、誰が関与し、何が起きたのか)
日向事件は1981年(昭和56年)6月24日、宮崎県警が北朝鮮工作員・黄成国(斉藤幸雄)を逮捕したことで発覚しました。黄は前年1980年6月、密命を帯びて北朝鮮の工作船で宮崎県日向市の小倉ヶ浜海岸に密入国していました。戦前に徴用工として日本に滞在した経験もある黄は、北朝鮮当局から再びスパイとなる訓練を受け、祖国の指令を受けての再潜入でした。その任務とは、「高麗民主連邦共和国」構想(北朝鮮の体制を維持したまま南北統一を図る構想)の実現のため、日本を拠点に在日韓国・朝鮮人を工作し、韓国社会に浸透させることでした。
黄成国は密入国後、東京にある在日朝鮮人女性(G女、当時52歳)の自宅をアジトとしました。G女は北朝鮮に家族を持つ人物で、黄をかくまっていた協力者でした。黄はそこを拠点に、日本国内の協力者たちとスパイ活動を開始します。彼の指揮下にいたのが映画監督の清本隆男(S、当時47歳)と、在日韓国人の実業家(M、当時62歳)でした。清本隆男は在日朝鮮人から日本に帰化した人物で、1970年頃から北朝鮮の工作員となっていたと言われます。映画監督という社会的地位を利用し、海外で北朝鮮の指令役と連絡を取ったり、韓国の知識人に接近して協力者を探したり、自衛隊基地の調査などを行っていました。一方、実業家Mは一時活動を停止していた元工作員でしたが、黄の再潜入を機に「再稼働」します。彼には韓国における地下組織づくりや、韓国の政治・経済・軍事情報の収集といった任務が与えられていました。表向きは日本企業の経営者として韓国に進出する準備を進め、頻繁に韓国へ渡航しては秘密任務を遂行していたのです。
しかし1981年4月、韓国国内で活動中だったこの実業家Mが韓国当局にスパイ容疑で逮捕されてしまいます。大切な協力者の逮捕により、自身の正体が露見することを恐れた黄成国は、北朝鮮本国からの「帰還命令」を受け取りました。黄は急遽、日本からの脱出を試みます。6月22日夜、潜入に使ったのと同じ小倉ヶ浜の海岸で北朝鮮の迎えの工作船と接触(「接線」)しようとしましたが、運悪く折からの台風による高波で船との合流は叶いませんでした。やむなく黄は浜辺近くの松林に身を潜め、空腹と疲労に耐えながら機会を窺いました。しかし迎えは現れず、ついに限界を迎えた黄が浜辺を彷徨っていたところを警戒中の宮崎県警に発見・逮捕されたのです。
黄成国の逮捕後、彼の周辺協力者たちも次々と摘発されました。7月10日には黄の片腕として動いていた映画監督・清本隆男が宮崎県警に逮捕され、自宅からは暗号表や乱数表、通信スケジュール表、暗号資金の受け渡し記録テープなど大量の証拠が押収されています。また、黄を匿っていたG女と、その仲間の男性H(32歳)も犯人蔵匿の疑いで検挙されました。押収品の中には精巧に偽造された外国人登録証明書や暗号メモ、短波無線受信機などがあり、日本国内で長期間にわたり秘密活動を行うための周到な準備が明らかとなりました。さらには、海岸の松林から発見された暗号メモの紙片に、ある“謎の薬品”を吹きかけると文字が浮かび上がるといった、スパイ映画さながらの特殊技術も確認されたといいます(※日本テレビ報道特集より)。黄の逮捕によって、北朝鮮が日本国内に張り巡らせていた地下工作網の一端が白日の下にさらされたのです。
逮捕から数ヶ月後、裁判で明らかになった事実は、日本社会に少なからず衝撃を与えました。黄成国は出入国管理令違反、外国人登録法違反、有印公文書偽造などの罪で起訴され、同年11月末に懲役1年6ヶ月の実刑判決を言い渡されます。清本隆男も出入国管理令違反(密入国ほう助)の罪で起訴され、9月末に懲役4ヶ月・執行猶予2年の有罪判決を受けました。また、G女には罰金4万円の略式命令(犯人蔵匿罪)、Hには執行猶予付きの有罪判決が下されたと伝えられています。北朝鮮工作員グループによる日本国内でのスパイ活動は、こうして一応の摘発・終結を見たのです。
社会的影響(当時の世論、制度や法律への影響、関係者のその後など)
日向事件が明るみに出た当時、一般の日本社会での反響は決して大きくありませんでした。冷戦下とはいえ、身近でスパイ事件が起きたという実感は希薄で、多くの人々にとって「遠い世界の出来事」に映ったかもしれません。しかし、この事件が持つ意味は極めて重大でした。戦後の日本で北朝鮮工作員が逮捕されるケースは他にも度々ありましたが、「工作員が完全に自供した唯一の事件」となったからです。黄成国は取調べにおいて、自らの任務や関与した工作活動の詳細まで包み隠さず語りました。その500ページを超えるという極秘の捜査資料から、北朝鮮の対日・対韓工作の実態が克明に浮かび上がったといいます。たとえば、日本国内の潜伏先ネットワーク、海外での資金受け渡しルート、暗号通信の方法、在日韓国人や留学生をリクルートして韓国に潜入させる計画など、その内容は多岐にわたりました。日本の治安当局は、この事件で得られた供述と証拠によって、北朝鮮の工作活動の全貌を把握するとともに、従来知られていなかった新たな事実にも気付かされました。その一つが、「北朝鮮工作員の不法出入国ルートの多様化」です。従来、北朝鮮の工作員は主に日本海側の海岸から密入国していると考えられていましたが、本事件により、南九州(太平洋側)沿岸からの侵入経路も現実に存在することが確認されたのです。実際、事件から数年後の1985年には日向灘(宮崎沖)で不審な工作船が発見されるなど、南九州方面での工作活動も相次いで発生しています。日向事件は、日本が地理的に四方の海岸線すべてで諜報活動の標的となっている現実を突きつけました。
法律や制度面への影響も看過できません。当時の日本には、「スパイ行為そのもの」を直接取り締まる法律が存在しませんでした。たとえ日本に害をなす諜報工作であっても、「工作員である」という理由だけでは逮捕できないのが実情だったのです。黄成国らに適用された罪名も、不法入国や偽造文書所持といった周辺事犯に留まり、スパイ活動そのものを処罰する法律はありませんでした。この法的な隙間については事件当時から指摘があり、実際に事件の翌年1982年頃から「スパイ防止法」の制定を求める声が保守系政治家を中心に高まりました。中曾根康弘首相(当時)は1985年、「日本はスパイ天国だ。重要機密を守る法律が必要だ」と国会で答弁し、同年には与党からスパイ行為防止法案が提出される事態に至ります。しかし、この法案は「国民の知る権利や報道の自由を侵害しかねない」としてマスメディアや世論の強い反発を招き、審議未了で廃案となりました。結局、日本で本格的なスパイ防止法が成立することはなく、黄成国のような外国工作員に対しては現在も出入国管理法違反や国家公務員法(機密漏洩)など個別の法律で対応するしかない状況が続いています。日向事件は、日本の法制度の不備を浮き彫りにし、国家安全保障に関する議論を喚起する契機ともなりました。
関係者のその後にも、それぞれのドラマがありました。黄成国本人は刑期満了後に釈放され、北朝鮮に送還されたとも伝えられます(詳細な経緯は公表されていません)。彼のかつての協力者だった実業家Mは、韓国で国家保安法違反に問われ死刑判決を受けたとされています。実際に処刑が執行されたか定かではありませんが、祖国に忠誠を尽くしたつもりの在日同胞が非業の最期を迎えた可能性が高いのです。映画監督の清本隆男は執行猶予付き判決で社会復帰を許されたものの、その後公の場に姿を見せることはなく、事実上映画界から姿を消しました。北朝鮮に利用された在日スパイの末路として、清本の存在はひっそりと歴史の陰に沈んでいったのです。そして何より、日本社会全体がこの事件から汲み取るべき教訓がありました。それは「平和に見える日常の裏で、知らぬ間に人々が国家の論理に巻き込まれている」という現実です。1980年前後、日本各地では行方不明事件が相次いでいました。その中には北朝鮮による日本人拉致が強く疑われる失踪も含まれていたことが、後の調査で判明しています。宮崎県出身の原敕晁さん拉致事件(1978年)など、北朝鮮による拉致被害はまさにこの頃、水面下で進行していたのです。黄成国の供述の中に拉致に関する言及があったかどうかは定かではありません。しかし日本当局は日向事件の段階で、北朝鮮が日本国内で秘密裏に工作員を動かし、必要とあらば拉致などの違法行為も辞さない危険な国家であることをうすうす認識していたとも言われます。残念ながら当時その事実が広く共有されることはなく、拉致被害者の家族たちは長く苦しい年月を耐えねばなりませんでした。「もっと早く真実を公表していれば…」という無念の声も、後に聞かれるようになります。
報道の扱い(事件当時のメディア報道の姿勢や変化、問題点など)
1981年当時、日向事件のニュースは一部で報じられたものの、その扱いは決して大きくありませんでした。地方で発生したスパイ摘発劇は、新聞の社会面で短く触れられただけで、多くの国民は詳細を知る機会がなかったのです。当時のメディアには、「北朝鮮の工作員が暗躍している」という事実を過度に刺激的に報道すれば、在日コリアン社会への偏見や国際緊張を煽りかねないという配慮もあったと考えられます。加えて、先述のスパイ防止法案を巡る議論でも明らかになったように、報道関係者の間には国家による情報統制への警戒感が強く、「スパイ事件」を必要以上にセンセーショナルに取り上げることへの慎重な空気があったとも言われます。結果として、日向事件で浮かび上がった数々の衝撃的事実(北朝鮮のスパイ網の存在や、日本国内での工作活動の実態など)は、当時の一般報道では深掘りされずに終わりました。それはある意味で「知らされないことによる平穏」でもありましたが、一方では国民の危機意識が高まらず、拉致問題などへの対応の遅れにもつながったとも指摘されています。
時が経ち、21世紀に入って北朝鮮拉致問題が大きく報道されるようになると、メディアの姿勢にも変化が現れました。2002年に北朝鮮が日本人拉致を公式に認めたのを機に、過去の諜報事件が改めてクローズアップされるようになったのです。日向事件もその一つでした。事件から40年以上が経過した2022年、日本テレビは独自に入手した極秘捜査資料をもとに、日向事件の真相に迫る特集報道を行いました。そこでは、当時の取り調べ官のエピソードに焦点を当て、「ある取調官の機転」と題したドキュメンタリーとして黄成国の“完全自供”の内幕が紹介されました。また、当時押収された暗号通信メモの解析や、工作員たちの潜伏ルートを地図化した再現映像、関係者の証言なども盛り込まれ、事件の全貌が初めて一般視聴者にも分かりやすく伝えられたのです。他のメディアも、拉致問題に関連付ける形で日向事件を振り返る記事を配信し、「もしあなたの身近で“拉致”が起きていたら…?」という問いかけとともに、当時見過ごされていた教訓を伝え始めています。
こうした報道の変化の背景には、「過去の過ちを繰り返さない」というメディアの自己検証の意図も感じられます。日向事件当時、私たちはどこか他人事としてスパイ事件を受け流してしまっていました。しかし、平穏な日常の陰で起きていた出来事に光を当て直すことで、初めて見えてくる真実があります。メディアは今、その役割を果たそうとしているのです。その一方で、当時の報道姿勢について「拉致被害者救出のチャンスを逃したのではないか」「もっと積極的に事実を伝えるべきだったのではないか」という批判の声があるのも事実です。当時の状況下でどこまで報じ得たかは簡単には測れませんが、報道が果たすべき使命について改めて考えさせられる点と言えるでしょう。
人間ドラマの視点で振り返る日向事件
日向事件は、一見するとスパイ摘発という国家安全保障の硬い話題です。しかし、その裏側には一人ひとりの人間ドラマがありました。北朝鮮から送り込まれた黄成国は、祖国の理想に人生を捧げた工作員でした。老境に入ってなお危険な密航に身を投じ、日本で密かに諜報活動を続けた彼の胸中には、「祖国統一」という大義への信念と、日本で暮らす人々への戸惑いが交錯していたかもしれません。実際、逮捕されたとき黄は懐に青酸カリの小瓶を忍ばせていたと言われます。任務が露見すれば自決しようという覚悟を持っていたのです。それほどまでに堅固だった男の心を溶かしたのが、一人の日本人警察官の優しさでした。極度の飢えと渇きに苦しむ黄に食事を与え、風呂に入れてやり、「あなたはもう一人じゃない」と兄弟の契りを結んで寄り添ったその姿。国家もイデオロギーも超えた人間同士の情が、国境を越えた真実の吐露を引き出したのです。
黄成国の語った真実は、私たち日本人にとって決して他人事ではありませんでした。彼がいた時代、その暗闇では、日本人拉致という痛ましい犯罪が進行し、多くの家族の人生が引き裂かれていました。黄自身がそれに直接関与していなくとも、彼が属した組織は同じ手で日本人をさらっていた可能性があります。そう思うとき、事件の被害者とは誰なのか、改めて考えさせられます。拉致された被害者とその家族は言うまでもなく、清本隆男のように北朝鮮に利用され罪を犯した在日韓国・朝鮮人もまた、広い意味でこの事件の被害者だったのかもしれません。故国と暮らす国とのはざまで翻弄され、人生を狂わされた人々――日向事件はそんな人間の悲哀を浮かび上がらせています。
事件から四十年以上が経過しました。冷戦は終結し、北朝鮮による拉致問題も国際社会で周知の事実となりました。それでも、黄成国が彷徨った日向市の静かな海岸線は今も変わらず波音だけを響かせています。白砂青松の美しい小倉ヶ浜は、夏になれば家族連れやサーファーで賑わう穏やかな浜辺です。その砂の上にかつて一人の工作員が残した足跡は、とっくに潮風に消え去りました。しかし、あの事件が教えてくれた教訓――「平和な国にも見えない闇は存在し、勇気ある告白と思いやりがその闇を照らす力となる」――は、決して消えることなく私たちの胸に刻まれるべきではないでしょうか。
日向事件は、単なるスパイ摘発事件ではありません。国と国、人と人の狭間で引き裂かれた人間模様の悲劇であり、そして同時に、一筋の温かな心が真実を解き放った希望の物語でもありました。当時それを十分に伝えきれなかったメディアも、いま改めてこの物語を掘り起こし、私たちに問いかけています。「もしあなたの人生に拉致が起きていたら?」と。私たちは二度と過ちを繰り返さぬよう、過去から目をそらさず、学び続けなくてはなりません。日向事件は、今なお色褪せることのない警鐘として、そして人間の絆の尊さを教えてくれる物語として、後世に語り継がれていくことでしょう。
参考資料:
- 宮崎県警察による日向事件の検挙概要(昭和57年警察白書)npa.go.jpnpa.go.jp
- 黄成国の供述内容と捜査結果(日本テレビ報道特集、極秘捜査資料)news.ntv.co.jpja.wikipedia.org
- 日本政府・警察当局の発表および調査会資料(特定失踪者問題調査会ニュース)chosa-kai.jppref.miyazaki.lg.jp
- 裁判記録に基づく関係者の判決内容(宮崎地方裁判所判決要旨)ja.wikipedia.orgja.wikipedia.org
- 北朝鮮工作員事件に関する書籍・研究(清水惇『北朝鮮情報機関の全貌』など)ja.wikipedia.orgja.wikipedia.org
podcasts.apple.comja.wikipedia.orgなどの出典は、当時の報道記録および後年の報道特集に基づく一次情報です。数字は参照箇所を示しています。


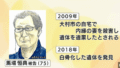
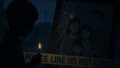
コメント